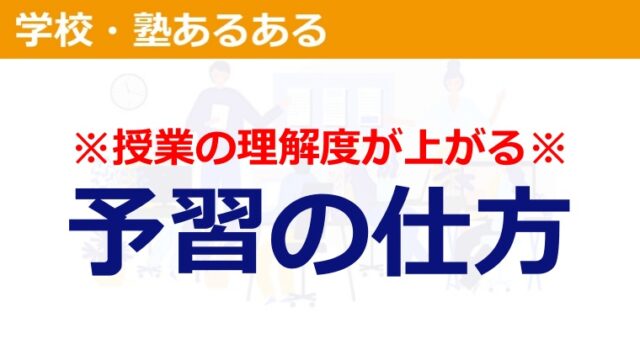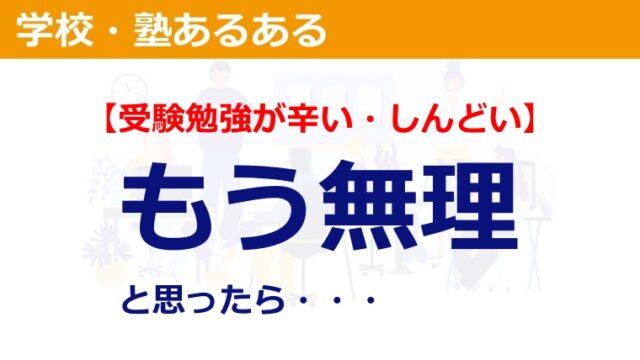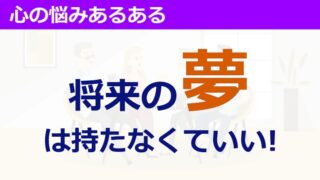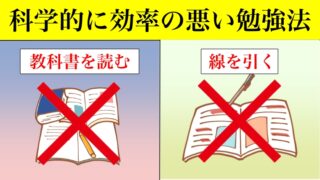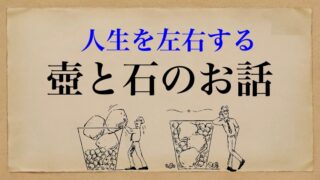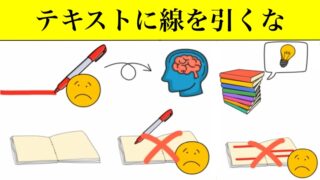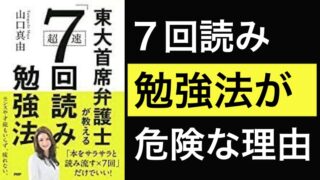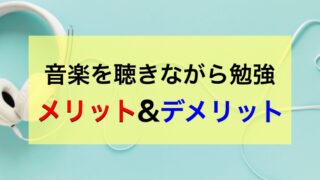志望校って決まりました?
一応決まってますか、そうですか。
じゃあ、どうやって志望校を決めましたか?
もしかして、現在の偏差値だけで決めましたか?
うーん。志望校選びはもっと慎重であるべきです。
しかし、悲しいことに、こんなコメントをもらったことがあります。
先生「う~ん、この偏差値だとちょっと危ないから、W大じゃなくてH大を第1志望にしてみない?」
生徒「……はぁ」
こんな決め方は最悪ですね。
決して、今の偏差値だけで志望校は決めてはいけません。。じゃあ、どうやって決めていけばシェアします。
じゃあど~する?

- 1.将来のことを考える。
- 2.何か興味があるかを考える。
- 3.ブランドで決める。
- 4.実際に、その学校に行ってみる。
- 5.偏差値はあくまで参考程度にする。
1.将来のことを考える。
将来のことを考えるのは大切だと思います。
当然、まだまだ漠然としたことしか考えられないかもしれませんが、それは受験をするうえで、志望校決定だけでなくて、モチベーションにもつながるので、ぜひ考えてほしいですね。
2.何か興味があるかを考える。
これが志望校決定のメイン材料になるかもしれませんね。
自分の興味があることから学校を探していく。
そうすると、本当に自分にとっていい学校がきっと見つかると思います。
3.ブランドで決める。
もし将来なりたいものや興味があることがなかったら、ブランドで選ぶのもありだと思います。
簡単にいえば、人から「すごい。」と言われる学校ですね。
ただ、ブランドで決めると、後々モチベーションが維持しづらくなるので注意です。
4.実際に、その学校に行ってみる。
同じレベルの学校でも、立地はもちろん校風もそうとう違います。
数年間通うことになる学校なので、オープンキャンパスや文化祭などの機会には見学に行きましょう。
5.偏差値はあくまで参考程度にする。
PCPCに模試のデータなどが入ってて、先生との面談のときに偏差値を基準に志望校を決めます。
偏差値は参考程度にしましょうね。
というか、学校によって出題傾向など、かなりの偏りがあるので、模試の結果など無視してもいいかもしれません。
まとめ
とにかく「自分で考えて」決めてください。
まあ、すべてに言えることは、『受験に関する情報を集め、自分で考えることですね!』
受験は情報収集戦という性格ももっているのでね笑
そして、必ず自分で考えるんです!
よく、
『数学の勉強はこうしろ!』
『受験で成功するにはこうしなきゃいけないんだ!』
などと言う人や、書いている勉強本が世の中には多いですね。
私はそういう押し付けるようなことは好きではありません。
だから、いつも解決方法は1個ではなく5個くらい提示してるんです。
その中から、自分に合いそうなのを選ぶもよし、選ばないもよしって感じなんです。とにかく自分に必要なものを取捨選択するって結構重要なんです。
先生や親に「ここ受けなさい」と言われても、最終決定は自分でしてね。
みんてぃあ