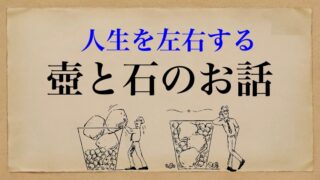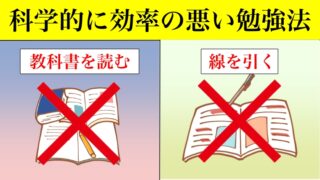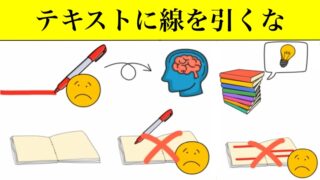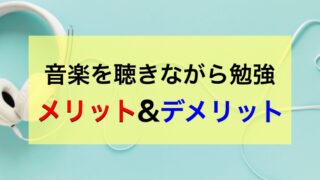先日、受験生から『問題集をやったのに、テストで解けない!』という相談を受けました。
普段、担当してる子ではなかったので、詳しく聞くとどうやら問題集の使い方が悪いと感じました。
『問題集は一回解いて、ハイおわり』という考えが高校生の間で蔓延してるみたいですね。
それではいけません。
あなたも、勉強する際に問題集を使用していると思います。
学校から配られたものや、塾に通っている人は塾の教材などいっぱい使っている方もいると思います。
ちゃんとすべて消化できてますか?
多くの問題集を使うと消化不良で終わる場合も結構ありますね。
では、問題集の使い方のヒントをシェアします。
じゃあど~する

- 1.○×△を書きこむ。日付も。
- 2.何度も解く。何度も見る。
- 3.奇数番号の問題だけやる。
- 4.わからないところには、ふせん。
- 5.問題集を開いて、授業を聞く。
どうですかね?
1個ずつ解説していくよ。
1.できない問題を減らすために、○×△を書きこむ。日付も。
問題を解いたら、日付と、
- できた問題=○、
- できない問題=×、
- 途中までわかるとか計算ミス=△
みたいにチェックしましょう。
テスト前は、×と△を重点的にやるようにすれば、どんどんできる問題が増えて、効率がいい。
2.何度も解く。何度も見る。
何度も解きましょう。
よく、「問題集は3回解け。」みたいに言う先生もいますが、回数は人によって違います。
見るだけでもいいので、こまめに復習してみては?(特に受験生は、長期記憶に変換する必要あり)
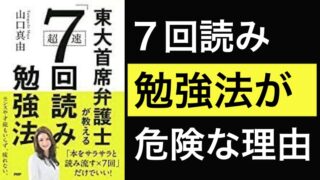
3.めんどくさかったら、奇数番号の問題だけやる。
完璧主義になってしまうと、勉強がおっくうになってしまいますそこでこのワザ。
2日かけて問題集を1周するより、奇数番号だけで1日1周を2日続けてやる方が、スピード感もあるし、記憶にもやさしいです。
お試しあれ。
4.わからないところには、ふせん。
問題集を進めてると、どうしてもわからない問題が出てきます。
そこで、「うーん……」って悩むのは時間の無駄かも。
「?」マークをつけたふせんを貼って目立たせて、次の日さっさと友だちや先生に質問しちゃいましょう。
5.授業中に問題集を開いて、授業を聞く。
普通の人は、授業を聞いてから、テスト前に問題集をやります。
しかし、実はこのやり方無駄が多いんです。
「明治維新とは?」みたいな質問文を確認してから、授業を聞くと、内容が頭に入りやすい。これは魔法のアイデアです。
まとめ
単に解く回数だけが大事なわけじゃない!
- 「どの問題を」
- 「どのように」
- 「何回解くのか」
この3つがとても重要!
1〜5のうち、あなたにどの勉強法が合うかはわからないけど、自分に合いそうなものを選んで、行動してみてね。
みんてぃあ
補足
問題集の選び方について書いておきますね。
[選び方]
- ネットで調べる
- 実際書店に行って手にとって自分に合うか見極める
では解説しますね!
①ネットで調べる
ネット上に「参考書、問題集レビュー」を載せているサイトが結構あるのでそれを見たり、Amazonのカスタマーレビューを参考にするのもいいかもしれません。
①書店に行く
いくらネットで調べても本当に自分に合うかどうかは分かりません。
だから、ネットである程度買おうとする参考書や問題集の数を絞ったら、やはり自分の目で見ないといけません。
この時のポイントとしては
- 「奥付を見る」
- 「パラパラっと見て6~7割はとけそうだと思うもの!」
を選ぶことですかね。
奥付をみるのは、出版年を見るってことです。あまり古いのは今の入試に対応できなかったり、逆にレベルが高すぎたりするので注意ですね。
そして結構重要なのが、6~7割はとけそうな物を選ぶ!ってことですね。
たまに、受験生で難問ばっかり載っている問題集を使っている人がいます。
決して悪いとは思いませんが、「本当にその難問に挑戦できるくらいの基礎力はついているの?」と思います。
受験生の目標は「入試で満点をとること」ではなく、「合格点を1点でも超えること」なのでね、
まずは標準的な問題が解けるようになりましょう。